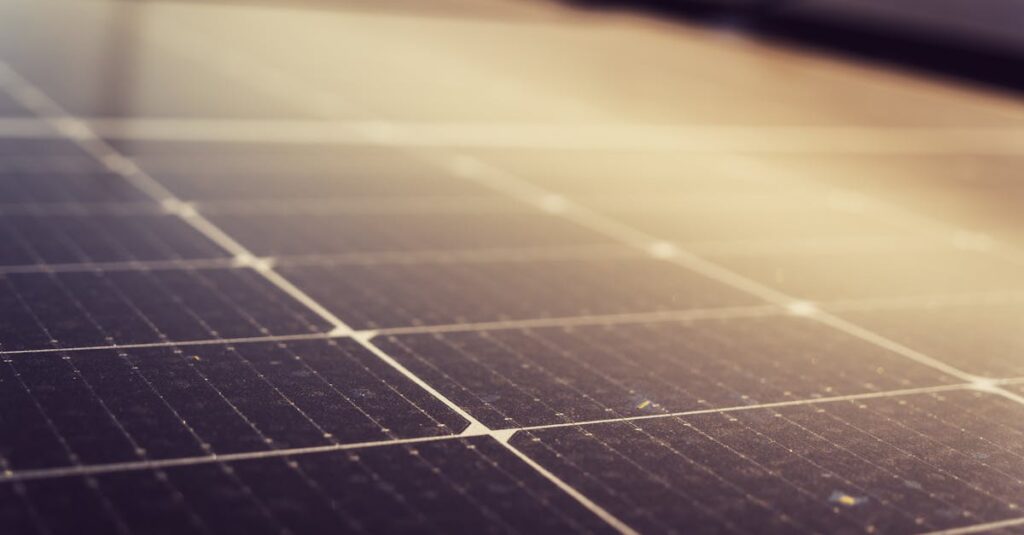木工を行う際、使用する機械や工具の動力源はさまざまです。作業環境や用途に応じて、適切な動力を選ぶことが作業効率を向上させるポイントになります。ここでは、人力、電力、バッテリー、圧縮空気を活用するツールについて解説します。
1. 人力
手加工
手作業で行う木工は、電力を使用せず、細かな調整がしやすいのが特徴です。ノコギリ、カンナ、ノミ、ヤスリなどの手工具を使うことで、伝統的な木工技術を活かした作業が可能になります。静音性が高く、屋外や電源のない場所でも作業ができるのがメリットです。
機械を人力で動かす
手加工以外にも人力で機械を動かす方法もあります。
Amazonにて足で踏む力で木工旋盤をする機械のつくり方のガイドブックがありました。(英語)
糸紡ぎ機にも似ていますが、こういう人力の機械の自作も面白そうです。
Make Your Own Treadle Lathe: Full Color Edition
2. 電力
商用電源
木工機械の多くは電源を使用します。一般的な電力供給には以下の2種類があります。
本格的な工房をつくる場合を除き、家庭では単相100Vを使用するのが通常です。
- 単相100V:家庭用電源で、電動工具の多くが対応しています。
- 三相200V:工場や大型機械向けで、パワーが必要な木工機械に適しています。
ポータブル電源と太陽光発電
近年では、ポータブル電源を活用することで、屋外作業や電源のない場所でも電動工具を使用できるようになっています。特に、ECOFLOWのような高性能ポータブル電源は、太陽光パネルと組み合わせることで、再生可能エネルギーを活用した持続可能な作業環境を構築できます。
わたしはECOFLOWのDELTA2とソーラパネル160Wセットを使用しています。天気の良い日に太陽光パネルとポータブル電源で充電して、ポータブル電源からマキタのバッテリーへ充電しています。今買うのであれば後継機のDELTA3を選ぶと思います。
災害対策にもなりますし、車に積んでキャンプ時の電源確保や移動式工房にも活用できたらと思っています。
3. バッテリー駆動
電動工具メーカーの多くは、コードレスで使えるバッテリー駆動のツールを提供しています。代表的なメーカーとしてマキタとHiKOKIがあります。
マキタのバッテリーの特徴
- 18V・40Vmaxシリーズが主流
- 互換性が高く、多くの工具で共通バッテリーが使用可能
- Li-ion 18Vシリーズは幅広い機器ラインナップ
HiKOKIのバッテリーの特徴
- 18V・36V(マルチボルト)シリーズ
- マルチボルトは、36Vと18Vの両方で使用可能
- ハイパワー工具にも対応
バッテリー駆動の工具はコードレスで取り回しが良く、屋外作業や電源のない場所でも活躍します。
マキタとHIKOKIどっちにするか問題
木工をはじめて機械を選定するときに悩むのが、マキタとHIKOKIどっちが良いかということです。
わたしもとても悩んだ末に、マキタにしました。理由としては「優先して使いたい機器のメーカーがマキタだったから」というところです。
コスパでいうとコードありが断然良いのですが、作業的にはトリマーと丸鋸はコードレスにしたかったのでその前提で検討、
トリマーはマキタ製RT50Dが良かったのでこれを基準にしました。その次にRT50Dの18Vバッテリーを使い回せる丸鋸を探してHS631Dにしました。
自分の工房の機器のメーカーを揃えたいという思いはありましたが、ボール盤、ディスクサンダー、その他そのジャンルでそれぞれ自分にとっていちばん良い機器を選定していくと、結局メーカーがバラバラになるのは避けられないので、メーカー統一優先よりもジャンルで評判の良い機器を選択することを優先しました。
いずれHIKOKIの機器やバッテリーも導入するときがきっとくると思います。
充電器・バッテリーセットにはケースもついてきます
マキタを選定される場合
購入方法としては
- 本体+充電器・バッテリー・ケース のセットで購入
- 本体のみ +それ以外を単品で購入
があります。
どちらがお得か比較してみると(下表参照)定価で比較するとセットのほうが高く、Amazon実績価格では若干セットのほうがやすいですが、ほぼ同じという感じです。
セットではケースが付属しますのでケースが不要な場合は、単品で購入するのもありかと思います。
わたしはトリマーのケースが欲しかったのでいちばん初めにトリマーのセット(RT50DRG)を購入、丸鋸は本体のみで購入しました。
| 単品定価(Amazon実勢価格) | セット定価(Amazon実勢価格) | |
|---|---|---|
| 本体 RT50D | ¥30,800 (19449) | RT50DRG ¥68,900(45475) |
| バッテリー BL1860B | ¥24,400 (14273) | |
| 充電器 JPADC18RF | ¥7,900 (8082) | |
| ケース | ¥4,173 メーカー公表なしのため Amazon実勢価格のみ | |
| 計 | ¥66,600 (45977) | ¥68,900 (45475) |
カッコ内がAmazon実績価格(2025/3/1時点)です
スライドソーはHITACHIのコードタイプにしています。
4. 圧縮空気(エアツール)
エアツールは、圧縮空気を使用することで高い出力と軽量性を両立できます。主にエアコンプレッサーと組み合わせて使用します。
なかなか個人の木工でエアツールを導入する人は少ないかもしれませんが、木工には非常に便利です。具体的には以下の用途で使用できます。
エアツールの種類と用途
- ブロアー:粉塵や木くずを吹き飛ばすのに便利
- スプレーガン:塗装作業に使用
- ピンタッカー:細い釘を打ち込むのに適している
- ディスクサンダー:研磨作業に使用
エアツールは、長時間使用してもモーターの発熱が少ないため、連続作業にも向いています。ただし、コンプレッサーの準備が必要であり、動作音が大きい点には注意が必要です。
とくに木工ではブロアーは必須ツールです。粉塵を吹き飛ばすにはもちろん、塗装前の素地調整のあとにブロアーでしっかり粉塵をとばすことで塗装がきれいに仕上がります。タッカーもあると仮止めや布地の抑えに重宝します。
わたしはエアコンプレッサーはミナトの「エアコンプレッサー 静音オイルレス型 CP-61Si エアーツール2点付き」を選定しました。
コンプレッサー系はたくさんメーカーがありますが、公式サイトでわかりやすく商品説明されていてユーザーフレンドリーな印象だったのでミナトさんにしました。
まとめ
木工で使用する動力源には、人力、電力、バッテリー、圧縮空気の4種類があります。用途や作業環境に応じて適切な動力源を選ぶことで、効率的に作業を進められます。最近では、ポータブル電源やバッテリー工具の進化により、より自由度の高い作業環境が実現できるようになっています。自分のスタイルに合った動力源を選び、快適な木工ライフを楽しみましょう!